団体信用生命保険(団信)とは?加入条件・何歳まで入れるかを解説
公開日 2024/04/30
最終更新日 2025/03/22

また、不動産投資ローンにも団信が付くことがあります。
団信は、ローンの契約者に不測の事態が起きた場合に、ローン残高を肩代わりして不動産や家族の生活を守ってくれる保険です。
団信に加入していない場合、万が一の際に遺された家族に大きな負担がかかるため、団信は欠かせない存在といえます。
今回は、団体信用生命保険(団信)とは?加入条件は?といった基礎知識や、団信の種類、審査基準などについて解説していきます。
団信の特徴を正しく理解し、加入時に適切な判断ができるようにしましょう。
>>賢くお金と知識を身につける【マネきゃん/Money Camp】団体信用生命保険(団信)とは
団体信用生命保険(団信)とは、住宅や投資用不動産の購入に際してローンを利用するときに加入する生命保険です。
ローン契約者が保険契約者となって加入し、死亡・高度障害状態となったときに、保険金によってローン残高を全額返済するものです。
団信の仕組み
生命保険は、保険金の受取人が契約者本人や家族など関係者であることが一般的ですが、団信の場合は、住宅ローンの債権者である金融機関が保険契約者であり保険金の受取人にも該当します。住宅ローンを利用する債務者が被保険者です。
団信の保険金が支払われるタイミングは、住宅ローンの債務者が死亡した場合や契約で定められる障害状態と認められた場合です。生命保険会社から保険受取人である金融機関に保険金が支払われます。
なお、支払われる保険金は、債務者の債務残高に相当する金額になります。住宅ローンの債権者である金融機関は、支払われた保険金を残債の支払いに充てることができます。
団信とローンの関係性
住宅ローンや不動産投資ローンは、数十年単位の長い期間をかけて返済していくことが一般的です。しかし、返済の途中で重い病気や事故などによって返済が困難になってしまう可能性も十分に考えられます。団体信用生命保険に加入することで、こうした万が一の事態に陥ったときにローンの返済が免除されることになり、遺された家族などへの金銭的負担をなくすことができます。対象不動産が住宅であれば、マイホームを手放す必要なくそのまま住み続けられ、投資用不動産であれば、資産を家族に遺すことができます。
団体信用生命保険(団信)のメリット
団信は、住宅ローンを借りる際にローン契約者が死亡した場合や高度障害状態になった場合に、住宅ローンの残債が保険金で完済される保険です。団信を利用することには以下のようなメリットがあります。1.万が一の際に住宅ローンの返済が免除される
団信に加入していると、契約者が死亡または高度障害になった場合、残りの住宅ローンの残債はすべて保険金で支払われるため、家族に返済負担がかかりません。これにより、残された家族は住宅ローンの返済に苦しむことなく、住み続けることができます。2.三大疾病や特定の病気に備えた特約が付けられる
団信には、標準の死亡や高度障害に加えて、三大疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞)や特定の病気に備えた特約を付けることができます。特約を追加することで、がんや脳卒中、心筋梗塞などの重大な病気が発生した場合にも、ローンの返済が免除されるケースがあります。これにより、健康リスクに対する備えが強化されます。
3.標準の団信は追加コストなしで加入できる場合が多い
多くの場合、団信の保険料は金融機関が負担しており、金利に組み込まれています。そのため、標準的な団信に加入する場合、追加の保険料を支払う必要がないケースがほとんどです。一方で、三大疾病やがん保険などの特約付き団信では、通常の金利に上乗せされる形で保険料が加算されますが、それでも比較的手軽に大きな保障が得られます。
団体信用生命保険(団信)のデメリット団信は住宅ローンを利用する上で非常に有益ですが、以下のようなデメリットもあります。
1.契約内容の途中変更ができない
団信は一度契約すると、契約後に特約の追加や内容の変更ができないケースがほとんどです。例えば、住宅ローン契約後に三大疾病特約を付けたいと考えても、途中から追加することはできないため、事前にしっかりとプランを検討しておく必要があります。契約前にどの保障が必要かを十分に検討し、将来的な健康リスクを見越しておくことが重要です。
2.夫婦での収入合算やペアローンで不便になる場合も
夫婦で収入合算やペアローンを利用する場合、団信の仕組みが不便になることがあります。例えば、収入合算をしている場合、団信はローン契約者(被保険者)にのみ適用され、連帯保証人には適用されません。つまり、パートナーが病気や事故でローン返済が困難になった場合でも、団信の保障は適用されず、返済が続くことになります。
また、ペアローンの場合もそれぞれのローンに対して個別に団信が適用されます。仮に一方の配偶者が亡くなった場合、その配偶者に割り当てられたローン分だけが保険で返済され、残された配偶者は自身のローンを引き続き返済しなければなりません。
3.健康状態による加入制限がある
団信には健康状態による審査があり、既往歴や持病がある場合には団信に加入できないことがあります。この場合、代替手段として他の生命保険や収入保障保険を利用する必要があります。特に、団信加入が難しい場合は、ローン返済に備える別の方法を考慮することが重要です。
団体信用生命保険(団信)の加入条件は?
団体信用生命保険の加入条件は大きく3つあります。加入条件1.これからローンを契約する人であること
団体信用生命保険への加入は、住宅ローンや不動産投資ローンの新規借り入れ、または借り換えをする人に限られます。また、一般的に、団体信用生命保険に加入したあとはプランを途中で変更することはできません。加入条件2.所定の健康基準をクリアしていること
団体信用生命保険は、被保険者であるローン契約者が返済不能になった際に、保険会社から金融機関へ「保険金」としてローン残高が支払われるものです。そのため、通常の生命保険と同じように、保険加入者は加入時に現在の健康状態や持病の有無、既往歴といった健康状態を告知する必要があります。このとき、所定の基準を満たしていない場合は団体信用生命保険に加入できません。その場合は、加入条件が緩和されている「ワイド団信」を選ぶこともできます。
加入条件3.年齢の条件を満たしていること
団体信用生命保険は、ローンに付随する生命保険であるため、そもそもローンを借りられない低年齢や、返済に無理が生じる高年齢では加入ができません。具体的な条件については次の項で詳述します。団体信用生命保険は何歳まで入れる?
団体信用生命保険に何歳まで加入できるかは、団信の種類や金融機関(またはその引受保険会社)によって異なる場合があります。住宅金融支援機構が提供する「フラット35」の団体信用生命保険(一般団信)の加入可能年齢は、満15歳以上、70歳未満となっています。また、後述する団信の種類によっても加入できる年齢に違いがあります。例えば、がん団信や三大疾病保証付き団信の場合は、満51歳未満(返済時・満80歳未満)としているケースが多く見られます。また健康条件の緩いワイド団信は、そのぶん年齢の制限を厳しくしており、多くの金融機関でがん団信などと同様に満51歳未満としています。
>>老後の資産づくりに最適な方法とは?
団体信用生命保険(団信)に入れない人とは
ここまで述べたように、団体信用生命保険に加入するには、保険会社による所定の審査を受けなければなりません。つまり、誰でも団信に加入できるわけではありません。引き受けてもらえなければ、住宅ローンそのものも利用できなくなってしまいます。そして、団信の審査基準は各社で異なり、開示されていません。ただし一般論として、団体信用生命保険も保険商品のひとつであるため、保険金の支払いリスクが高い人は加入が難しくなるということがいえます。
審査が通りにくい人とは?
審査に落ちる可能性が高い人として一番最初に挙げられるのは、健康状態が良好でない人です。一般的に告知項目に該当しなければ、加入できる可能性は高いといえますが、該当したらかといって必ず審査に通るわけではないことも認識しておきましょう。また、プロボクサーやスタントマンなど死亡リスクが高い特殊な職業の人も、一般の人と比べると審査に落ちる可能性が高いといえます。なお、暴力団など反社会的勢力等の関係者は保険契約はできません。
団体信用生命保険(団信)と生命保険の違いは?
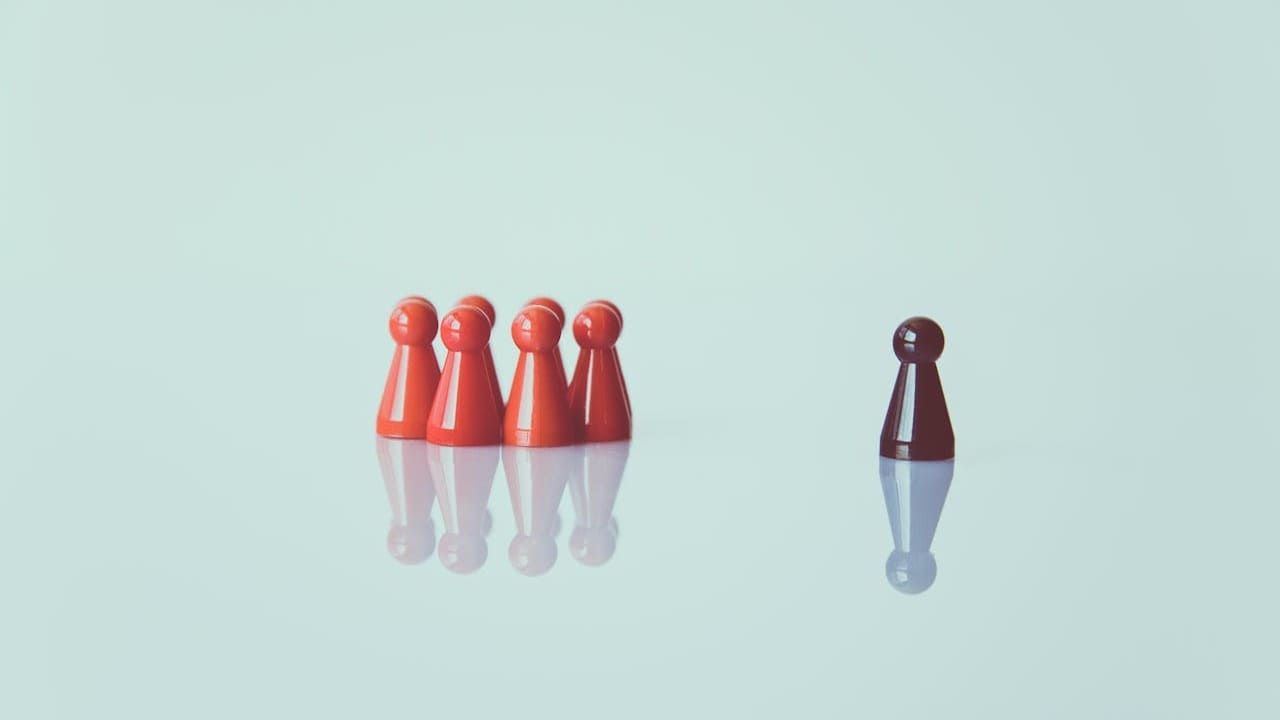 団体信用生命保険は保険商品の一つではありますが、一般的な生命保険とは特徴が異なる点がいくつかあります。主な違いを次の4つの点から解説します。
団体信用生命保険は保険商品の一つではありますが、一般的な生命保険とは特徴が異なる点がいくつかあります。主な違いを次の4つの点から解説します。違い1.保険料
まず一般的な生命保険の場合、保険契約者は振込や口座引き落としなど複数の支払い方法の中から選択して、「保険料」として支払います。しかし、団体信用生命保険の保険料は実質的に住宅ローン金利の中に含まれており、「保険料」として別で支払うことはありません。また、不動産投資ローンで加入が任意の場合は、加入することで保険料として0.2~0.3%程度の金利が上乗せされます。そのほか、通常の保険では加入時の年齢が若いほど安くなるのが一般的ですが、団体信用生命保険に関しては年齢や性別による保険料差はありません。
違い2.保険金の受取人
通常の生命保険では、被保険者が死亡した際の保険金は、保険契約者が指定した配偶者や子供などの法定相続人が受け取ることになります。一方の団体信用生命保険では、保険金は住宅ローンを契約している金融機関が受取人となります。支払われる保険金は住宅ローンの返済に充てられるため、保険契約者やその家族、親族などが受け取ることはできません。
違い3.保障期間
生命保険は、基本的に契約時に定めた保険期間中に保障を受けられます。中途解約した場合はその時点で保障が終了しますが、終身保険であれば一生涯、定期保険であれば予め定められている時点まで保障が続きます。一方の団体信用生命保険の保障期間は、住宅ローンの返済期間と連動しており、住宅ローンの返済開始から返済終了までが保障期間となります。そのため、繰上返済によって返済期間が短くなると、保障期間も契約当初より短くなります。
違い4.生命保険料控除
団体信用生命保険は生命保険料控除の対象にはなりません。生命保険料控除を適用するには、保険金受取人が保険契約者、または配偶者・親族である必要がありますが、団体信用生命保険の保険金受取人は、上述のとおり住宅ローンを契約した金融機関であるため、生命保険料控除の対象契約にはあたりません。団体信用生命保険(団信)の種類と保障内容
 団体信用生命保険は、商品の種類が多様化しており保障内容も異なります。ここでは、団体信用生命保険の主な種類5つとそれぞれの保障内容を紹介します。
団体信用生命保険は、商品の種類が多様化しており保障内容も異なります。ここでは、団体信用生命保険の主な種類5つとそれぞれの保障内容を紹介します。1.一般団信(特約なし)
特約がなにも付帯されていない「一般団信」は、被保険者(ローン契約者)が死亡もしくは高度障害状態になったときに保険金が支払われます。高度障害状態とは、病気や怪我等により、常に介護を要するなど著しく身体の機能が損なわれた状態を指しており、具体的には引受先である生命保険会社ごとに基準が定められています。
2.がん保障団信
がん団信は、「所定のがん(悪性新生物)」と診断確定された場合に保険金が支払われます。ただし、上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんについては保障対象外とされていることが一般的です。また、保障開始日から90日 (3カ月)以内にがんと診断確定された場合も保障の対象外となり、保険金を受け取れません。がん団信には、「所定のがん」と診断確定されたときにローン残高の50%が保障される「がん50%団信」と、ローン残高の100%全額が保障される「がん100%団信」の2種類があります。一般的に、がん50%保障は上乗せ金利なしで付けられる一方、がん100%保障は住宅ローン金利に0.1〜0.2%程度上乗せして加入できます。
3.三大疾病保障付き団信
三大疾病保障付き団信は、特約なしの一般団信で保障される「死亡・高度障害状態」に加え、三大疾病とされる「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」によって所定の状態となった場合に、住宅ローン残高の全額が保険金によって返済されます。がんの場合は、診断確定された段階で保障対象となる一方、急性心筋梗塞や脳卒中の場合は、診断されただけでは対象とならない商品もあります。その場合、保険会社ごとに定める所定の状態となった場合に保険金が支払われるため、加入前に条件をよく確認しましょう。上乗せ金利は金融機関ごとに異なりますが、0.2%前後が目安です。
4.八大疾病保障付き団信
八大疾病保障付き団信は、「死亡・高度障害状態」および「三大疾病」に加えて、「高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎」といった生活習慣病を含めた8つの病気によって所定の状態となったときに保険金が支払われます。保障内容は、診断されただけでローン残高が完済されるものや就業不能時に毎月の返済が免除されるものなど、疾病ごとにそれぞれ定められています。加入する場合、金利0.3%程度が上乗せされます。
5.ワイド団信
ワイド団信とは通常の団信よりも加入条件が緩和されており、健康上の理由で通常の団信に加入できない方向けの商品です。一般的に団信に加入する際には、現在の健康状態や過去の病歴などを告知しなければならないため、告知内容によっては審査に通らず、加入できないことがあります。ワイド団信は、通常の団信よりも告知項目が少なく引受基準が緩和されているため、高血圧、糖尿病、肝炎などの持病がある方でも加入できる可能性があります。ワイド団信の上乗せ金利の目安は0.3%程度です。
団体信用生命保険(団信)は自身に合ったものを選ぼう
今回は団体信用生命保険(団信)とは何か、またその加入条件などについて解説しました。団体信用生命保険に加入することで、住宅ローンや不動産投資ローンの返済が難しい状況になってしまった場合に備えられます。また、特約を付帯することで保障内容を幅広く設定でき、さまざまな不安にも対応できるようになっています。
ただし、保障を増やすとその分金利が上乗せになったりと負担が増えていく点にも気をつけましょう。ローンは大きな額を長期的に返済していくため、上乗せ金利なども考慮しながら自身の希望に沿ったプランを選ぶことが大切です。























