72の法則・100の法則・115の法則とは?複利効果を資産運用に役立てよう
公開日 2023/10/03
最終更新日 2025/03/04

資産運用でお金を2倍に増やすのは、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

そこで今回は、資産運用を始めるうえで知っておくと便利な3つの法則、「72の法則」「100の法則」「115の法則」を紹介します。

法則や複利を活かすことで、効率的に資産運用を進められるでしょう。
| この記事の要点まとめ |
|---|
|

>>【無料で10,000円分もらえてお得】今だけのキャンペーンまとめ
筆者も以下の通り、資産を増やせているサイト「クリアル」でのキャンペーンなのでぜひチェックしてください。

72の法則とは
72の法則とは、複利で運用した場合にお金が2倍になるまでの期間を把握できる便利な法則です。
以下の計算式のとおり、72を金利(利回り)で割ることで計算できます。
- 【72 ÷ 金利(%) ≒ 複利でお金が2倍になる年数】
では、100万円を年利5%で複利運用した場合を考えてみましょう。
計算式にあてはめると「72÷5=14.4」となり、100万円が2倍の200万円になるには約14年かかることになります。
また、「72の法則」の式を変形させることで「お金が2倍になる金利」も求められます。
- 【72 ÷ 複利でお金が2倍になる年数 ≒ 金利(%)】
例えば、10年で手元の資金100万円を2倍にしたい場合、「72÷10≒7.2」となり約7%の金利で運用する必要があります。
この算式で求めた利回りにあわせて、自分の資産形成に活用すべき金融商品を選ぶという使い方が可能です。
100の法則とは
100の法則とは、単利で運用した場合にお金が2倍になるまでの期間を求められる法則です。
次の式のとおり、100を金利(利回り)で割って算出します。
- 【100 ÷ 金利(%) ≒ 単利でお金が2倍になる年数】
最初に紹介した「72の法則」が「複利」で運用した場合に資産を2倍にするまでの期間を求める計算式。
それに対して、「100の法則」は「単利」で運用して資産を2倍にするまでの期間を求める計算式です。
単利とは、元金だけを対象にした金利の計算のことです。
複利のほうが早く増える
では、先程と同じ条件である100万円を年利5%で運用した場合を見てみましょう。
計算式を使うと「100÷5%≒20」となり、元手の100万円を2倍の200万円にするには約20年の年月が必要であると分かります。
年利(利回り)が同じでも、複利で運用した場合は約14年であるのに対して、単利で運用した場合は約20年と大幅に長くなってしまいます。
ここで気になってくる複利と単利の違いについては、後ほど解説します。
115の法則とは
115の法則とは、複利で運用した場合にお金が3倍になるまでの期間を把握できる法則です。
115を金利(利回り)で割って求めます。
- 【115 ÷ 金利(%) ≒ 複利でお金が3倍になる年数】
これまでと同様に、100万円を年利5%で運用した場合をみていきます。
「115÷5%≒23」となり、元手の100万円を3倍の300万円にするには約23年の年月が必要であると分かります。
年利5%で運用した場合、単利で約20年運用して資産がやっと2倍になるのに対して、複利運用なら約23年で3倍にもなるわけです。
明らかに複利のほうがメリットがありそうですが、複利と単利はどう違うのでしょうか。
複利と単利の違い
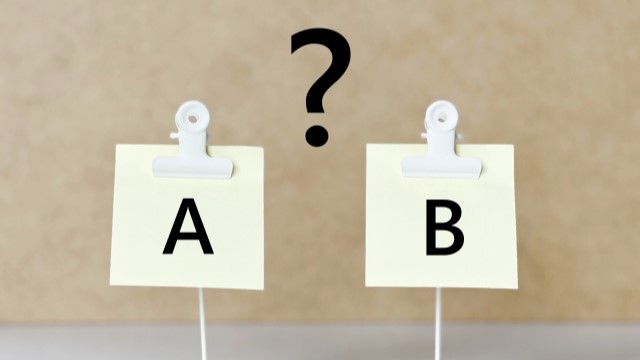
複利と単利はいずれも、利息の計算方法です。それぞれの計算方法と違いについて解説します。
複利
複利は、利息を元本に組み入れて、その合計を次の利息計算時に元本とします。
例えば、100万円を年利5%で運用した場合をみていきましょう。
最初の1年間の利息は、元本100万円の5%にあたる5万円です。
2年目は、1年目に受け取った利息が元本に組み入れられます。
そのため利息計算時の元本は105万円となります。
つまり、2年目の利息は元本105万円の5%にあたる5万2,500円です。
長期になればなるほど元本は増えていくため、利息もその分大きくなっていきます。
単利
単利は、最初の時点の元本に対してのみ利息がつきます。
例えば、100万円を年利5%で運用した場合の1年間の利息は5万円です。
2年目以降も元本100万円に対して利息が計算されるため、利息は毎年5万円となります。
複利と違って、元本の額がずっと100万円であるため、利息も毎年同じ金額です。
投資においては「複利」が圧倒的に有利
複利で運用するということは、もともとの手元資金に加えて運用で得られた利益も投資することになります。
つまり、得られた利益がさらに利益を生み出すため、運用期間が長くなるほど利息分の増加が加速します。
このようにして、お金が「雪だるま式」に膨らんでいくことが複利運用の一番のメリットです。
単利と複利の差は驚くほど大きい
では、単利と複利でどれほどの差が生まれてくるのでしょうか。
先ほどの事例と同様に100万円を年利5%で運用した場合、資産額にどのくらいの差が出てくるのかシミュレーションしてみましょう。
以下の表は、単利・複利それぞれで運用した場合に受け取れる利息です。なお、税金は考慮しません。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | ・・・ | 10年目 | 累計 | |
| 単利 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ・・・ | 5万円 | 50万円 |
| 複利 | 5万円 | 5万2,500円 | 5万5,125円 | ・・・ | 7万7,567円 | 約63万円 |
複利で10年間運用した場合の累計利息は約63万円となり、単利で運用した場合の50万円とは10万円以上もの差が生まれます。
もちろん、さらに運用を続ければ利息の差も広がっていきます。
効率的に資産形成を行うために、この複利の仕組みを積極的に活用したいものです。
複利の効果を得ながら資産運用する方法3つ

1.長期で運用する
複利の効果を高めるためには、長期目線での運用が鉄則です。短期間だと単利との差はそれほど大きくなく、十分な複利効果を享受できません。
時間を味方につけて、複利のメリットを最大限高めましょう。
もちろん運用を長期的に続ける中で、市場が暴落することも十分考えられます。
しかし、一時的な値下がりに焦って資産を手放してしまう、いわゆる「パニック売り」はとてももったいない行動です。
長期で運用するのであればなおさら、運用中に多少の価格変動はあるものと考えておきましょう。
一喜一憂しすぎず、当初の運用目的を思い出して長期投資を続けることが複利で資産を増やしていくポイントといえます。
2.再投資する
複利は、元本が大きければ大きいほど効果が上がります。
例えば、5%の利回りで元本100万円を運用する場合と、2倍の200万円を運用する場合とでは受け取れる利息も倍の差が出てきます。
元本100万円なら利息5万円、元本200万円なら利息10万円です。
つまり、できるだけ元本を増やすほうが効率的に資産をつくっていけるのです。
利益の再投資は魅力
元手資金を可能な範囲で増やすことも大切ですが、もちろん限界もありますし生活を圧迫するほど無理して投資に資金を回すべきでもありません。
そこで活用したいのが、運用によって生じた利益を再投資する方法です。
この利益が新たに利益をうみ、この仕組みこそが複利の魅力です。
【再投資には投資信託が最適】
投資信託の場合、「再投資型」の投資信託があります。投資信託は、運用によって得られた収益が投資家に「分配金」として還元されます。
この分配金を現金にせず、そのまま同じ投資信託を自動で追加購入するという仕組みが「再投資型」です。
自分で再投資をする手間もかからず、追加購入した分だけ運用資産も増えて複利効果を期待できます。
3.コスト削減する
コストにシビアになることも、複利効果を高めるうえでは重要です。
長期的な運用であればなおさら、コストは少しでも安いほうが利益を最大化できます。
手数料が低い商品を選ぶことが、結果的に運用に充てられる元本を増やすことに繋がります。
非課税制度で運用を有利に
また、コストは手数料だけでなく「税金」も挙げられます。
本来は、運用によって得られた運用益や分配金などに対して約20%程度の税率が課税されます。
しかし、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの税制優遇制度を利用して運用した場合は非課税となります。
これらは、積極的に活用して効率的な資産形成に役立てていきたい制度といえます。
複利で効率的に資産形成を
今回は、運用を始めるうえで知っておくと便利な3つの法則、「72の法則」「100の法則」「115の法則」と、複利の効果について解説してきました。
72の法則、100の法則、115の法則を知っていれば、資産運用によって達成したい目標金額に向けて、運用期間やどの程度のリスクをとるべきかが簡単にイメージできるようになります。
複利を活用すれば、余計なリスクをとらずとも長期的に運用することで資金を2倍にも3倍にも増やせる可能性が高まります。
複利のメリットを最大限に享受するためにも、できるだけ早くから資産運用をスタートさせましょう。
3つの法則は、資産を効率的に増やす上で大事な考え方です。
>>【無料で10,000円分もらえてお得】今だけのキャンペーンまとめ
筆者も以下の通り、資産を増やせているサイト「クリアル」でのキャンペーンなのでぜひチェックしてください。






















