高配当ETFはおすすめしない?デメリットや配当金生活できるかも解説
公開日 2025/10/29
最終更新日 2025/11/14

「配当金で毎月収入を得たい」
「高配当ETFなら安心して投資できそう」
そう考える人は多いでしょう。(筆者も高配当ETFに投資してきました)
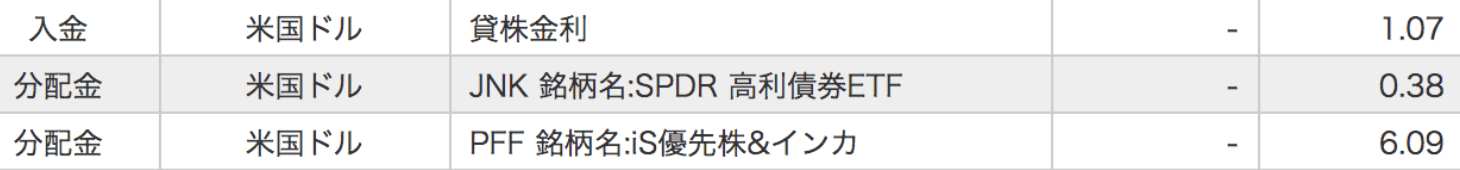
しかし実際には、「高配当ETFはおすすめしない」と言われることもあります。
この記事では、高配当ETFが抱える落とし穴や注意点をわかりやすく解説します。
メリット・デメリット、銘柄選びのポイントを丁寧に整理。
配当金生活を目指す際の現実的な見通しも紹介します。
投資初心者の方でも安心して理解できる内容です。
- ・高配当ETFは安定収入を得やすいが、成長性は低い
- ・高利回りの裏には株価下落や減配リスクが潜む
- ・分配金の自動再投資ができず複利効果を活かしにくい
- ・セクター偏重や為替変動などリスク分散が難しい面も
- ・目的とリスク許容度を明確にすれば長期運用の一手に
高配当ETFを日本株・米国株で買っていくなら、取引コストを抑えやすい松井証券が有利です。

1つの口座で日本株ETFも米国株ETFもまとめて取引でき、配当管理もしやすいです。
【こちらもチェック!】
>> 【無料でお得】松井証券キャンペーンまとめ|口座開設などで7000円分ポイント付与松井証券ではお得なキャンペーンも開催中なので、以下の公式サイトをチェックしてみてください。
\お得キャンペーンの詳細を知る/
高配当ETFとは?基本の仕組みと特徴を解説
まず、「高配当ETF」の仕組みを整理しておきましょう。
ETF(Exchange Traded Fund:上場投資信託)は、株式のように証券取引所で売買できる投資信託です。
その中でも、配当金や分配金が比較的高いものを「高配当ETF」と呼びます。
主な特徴は以下の通りです。
- 複数の高配当株をまとめて保有できるため、個別株より手間が少ない。
- 定期的な分配を受けやすく、安定した収入を重視する人に人気。
- 株価の値動きと配当の両方を得られるが、成長株とはリスク構造が異なる。
ただし、これらの特徴の裏には注意すべきリスクもあります。
【こちらもチェック!】
>> 買ってはいけない高配当株の特徴4選|失敗を防ぐ銘柄の選び方5つも解説高配当ETFは本当におすすめしない?その理由を紹介
「おすすめしない」と言われる理由は、以下のようなデメリットがあるためです。
理由①:値上がり益を得にくい
高配当ETFは利回り重視のため、成長企業の比率が低くなりがちです。
株価の上昇による利益(キャピタルゲイン)が得にくく、トータルリターンが伸びにくい傾向があります。
【こちらもチェック!】
>> やめとけ?高配当株おすすめしない?買ってはいけない銘柄とその特徴を解説理由②:高利回りは株価下落のサインかもしれない
利回りが高く見えても、実は株価下落によって一時的に上がっているケースもあります。
いわゆる“バリュートラップ”に陥る可能性があり、配当が減配・停止されるリスクも無視できません。
理由③:分散投資にならないことがある
高配当株は特定の業種(エネルギー・金融・公共事業など)に偏りやすく、ETFでも構成が集中する傾向があります。
結果として、市場全体の動きよりも特定セクターの影響を強く受けるリスクがあります。
【こちらもチェック!】
>> 【即日現金プレゼントも】無料登録でお金をもらえるキャンペーン、アプリまとめ理由④:自動で再投資できず複利効果が弱い
分配金を自動再投資できないETFが多く、自分で再投資の手続きをする必要があります。
複利運用を重視する人にとっては、やや手間が増える点がデメリットです。
理由⑤:自動積立に対応していない場合がある
インデックス投資信託と違い、高配当ETFは自動積立ができないケースがあります。
毎月の積立投資が難しいと、長期運用の効率が下がる可能性があります。
理由⑥:信託報酬などのコストがかかる
ETFには信託報酬(運用コスト)が発生します。
銘柄の入れ替えが多い高配当ETFでは、運用コストが高くなる場合もあります。
理由⑦:株主優待を受けられない
日本株の個別銘柄を保有する場合と異なり、ETFでは株主優待が受けられません。
優待目的の投資をしている人にとっては魅力が薄いでしょう。
理由⑧:為替リスクがある(海外ETF)
米国の高配当ETFを購入する場合、ドル建てでの取引になるため為替変動の影響を受けます。
円高時には、配当額が減るだけでなく元本割れのリスクもあります。
理由⑨:銘柄選びが難しい
利回りの高さだけで高配当ETFを選ぶのは危険です。
増配実績、財務状況、セクターの偏り、信託報酬などを総合的に判断する必要があります。
初心者には少しハードルが高い投資商品かもしれません。
【こちらもチェック!】
>> 最大5万円も!無料でアマギフ(Amazonギフト券)もらえるキャンペーンまとめ高配当ETFに投資するメリット
高配当ETFはデメリットばかりではありません。
高配当ETFには魅力もあります。
特に安定収入を重視する人にとっては、長期的な資産形成の一手となり得ます。
1. 定期的な配当金収入を得られる
高配当ETFの最大の魅力は、定期的に配当金を受け取れることです。
米国ETFの多くは年4回の分配があり、給与以外の収入源になります。
例えば年利3〜4%のETFを1,000万円分保有すれば、税引前で年間30〜40万円の配当が期待できます。
2. 少額で分散投資ができる
ETFは1口単位で購入でき、1本で数十〜数百銘柄に分散投資できます。
個別株投資に比べて少額で始めやすく、リスクを抑えながら安定的に運用できます。
3. 売買の自由度が高い
ETFは株式のように市場でリアルタイムに売買できるため、タイミングを選べます。
値動きに応じて戦略的に取引できる点は、通常の投資信託にはない利点です。
4. 配当を再投資して資産を増やせる
自動再投資はできなくても、自分で配当を再投資すれば複利運用が可能です。
配当を再投資し続ければ、「配当が配当を生む」資産成長サイクルを作ることができます。
手数料の安い証券会社でお得なキャンペーン中
高配当ETFを日本株・米国株で買っていくなら、取引コストを抑えやすい松井証券が有利です。

1つの口座で日本株ETFも米国株ETFもまとめて取引でき、配当管理もしやすいです。
【こちらもチェック!】
>> 【無料でお得】松井証券キャンペーンまとめ|口座開設などで7000円分ポイント付与松井証券ではお得なキャンペーンも開催中なので、以下の公式サイトをチェックしてみてください。
\お得キャンペーンの詳細を知る/
高配当ETFをおすすめする人・しない人
高配当ETFは、投資目的やライフステージによって向き不向きがあります。
おすすめしやすい人
以下、高配当ETFをおすすめしやすい人の特徴です。
・定期的な配当収入を得たい人。
・ある程度まとまった資金を持ち、安定運用を重視する人。
・個別株の選定や管理を省きたい人。
おすすめしない人
以下、高配当ETFをおすすめしない人の特徴です。
・資産を増やしたい成長志向の投資家。
・複利効果を最大化したい人。
・株主優待を得たい人。
高配当ETFの利回り比較と注目銘柄
次に、代表的な米国・国内の高配当ETFを見てみましょう。
米国株の高配当ETF
米国の高配当ETFは、世界中の投資家から人気を集めています。
なかでも「VYM」「HDV」「SPYD」は3大高配当ETFとして知られ、それぞれに特徴があります。
【こちらもチェック!】
>> 【VYMと比較】SPYDおすすめしない?メリットとデメリットや配当利回りを解説共通点として、いずれも安定した大型株を中心に構成され、年4回の配当が得られる点が魅力です。
【こちらもチェック!】
>> 【月20万】VYMで配当金生活シミュレーション!権利落ち日いつ?利回りや買い方も紹介人気銘柄のリスクとは?
ただし、銘柄構成や運用方針に違いがあり、リスクとリターンの性質も異なります。
| 銘柄名 | 正式名称 | 主な特徴 | 向いている投資家 |
|---|---|---|---|
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 配当利回りはやや控えめだが、銘柄数が多く分散性が高い。 銀行や消費財など幅広いセクターをカバー。 |
安定性・分散重視の人 |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF | 財務健全性の高い企業を厳選。 エネルギー・ヘルスケア・通信などのディフェンシブ銘柄中心。 |
守りの運用をしたい人 |
| SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | S&P500のうち配当利回り上位80社を均等加重で構成。 利回りは高いが値動きはやや大きい。 |
高配当重視・リスク許容度が高い人 |
この3つはいずれも長期保有に適していますが、重視するポイントによって選び方が変わります。
安定性ならVYM、守り重視ならHDV、高配当重視ならSPYDといった使い分けが一般的です。
低コストでお得!キャンペーンも開催中で人気の証券会社
高配当ETFを日本株・米国株でコツコツ買っていくなら、取引コストを抑えやすい松井証券が有利です。

1つの口座で日本株ETFも米国株ETFもまとめて取引でき、配当管理もしやすいです。
【こちらもチェック!】
>> 【無料でお得】松井証券キャンペーンまとめ|口座開設などで7000円分ポイント付与松井証券ではお得なキャンペーンも開催中なので、以下の公式サイトをチェックしてみてください。
\お得キャンペーンの詳細を知る/
国内の高配当ETF
日本株の高配当ETFも、個人投資家を中心に注目を集めています。
代表的な銘柄としては以下があります。
「日経高配当株50ETF(1489)」
「MAXIS日本株高配当70ETF(1577)」
「上場インデックスファンド日本高配当(1698)」
これらは東証一部(プライム市場)に上場する高配当株を中心に構成されており、年1〜2回の分配金を受け取ることが可能です。
日本株ETFのメリット
国内ETFのメリットは、円建てで取引できるため為替リスクがない点です。
また、日本企業の中には配当性向を高める動きが広がっており、今後も安定した分配が期待できます。
一方で、米国ETFに比べて銘柄数が少なく、流動性(売買のしやすさ)が劣る点には注意が必要です。
国内ETFを活用する際は、分配頻度や構成銘柄のバランスを確認し、長期的な安定配当を重視した銘柄選びが重要です。
高配当ETFの選び方・購入手順・NISA活用法
投資を始める際は、まず証券口座を開設しましょう。
NISA(つみたてNISA/新NISA)を活用すれば、配当などに対して非課税のメリットが得られます。
銘柄選定では、配当利回りだけでなく「増配実績」「運用コスト」「分散度合い」「為替リスク」なども確認することが大切です。
Q&A:高配当ETFのよくある疑問
配当金生活を目指すにはいくら必要?
わかりやすいように、税引き前で月10万円を得る場合で計算します。
年間配当利回り3%で月10万円(年間120万円)の配当を得たい場合、約4,000万円の投資元本が必要です。
利回り4%なら約3,000万円が目安です。
税金や減配リスクも考慮し、ETFだけに頼らず他の資産と組み合わせるのが現実的です。
配当金はどのくらいの頻度で支払われる?
ETFによって異なりますが、米国ETFは年4回、日本ETFは年1〜2回が一般的です。
複数のETFを組み合わせれば、年間を通して安定的に配当を得ることが可能です。
高配当ETFだけで生活できる?
理論上は可能ですが、実際には相当な資産規模が必要です。
多くの投資家は「生活費の一部を補う」目的で運用しています。
配当金は再投資すべき?現金で受け取るべき?
目的によって異なります。
資産を増やしたい人は再投資、生活費に充てたい人は現金受取がおすすめです。
初期は再投資で資産を育て、後半で現金化する二段階戦略が効果的です。
まとめ:目的と運用スタイルを明確にすれば高配当ETFは有効
高配当ETFは、「安定した収入」「手軽な分散投資」という魅力があります。
一方で、「成長性の欠如」「セクター偏重」「為替や減配リスク」など注意点もあります。
重要なのは、自分の投資目的とリスク許容度に合っているかを見極めることです。
資産を増やしたい人はインデックス投資との併用も検討し、長期的な視点で活用しましょう。
低コストで人気の証券会社でお得なキャンペーン中!
高配当ETFを日本株・米国株でコツコツ買っていくなら、取引コストを抑えやすい松井証券が有利です。

1つの口座で日本株ETFも米国株ETFもまとめて取引でき、配当管理もしやすいです。
【こちらもチェック!】
>> 【無料でお得】松井証券キャンペーンまとめ|口座開設などで7000円分ポイント付与松井証券ではお得なキャンペーンも開催中なので、以下の公式サイトをチェックしてみてください。
\お得キャンペーンの詳細を知る/





















