ファングプラス/FANG+おすすめしない?今後どうなる?デメリットと掲示板の声も紹介
公開日 2025/10/14
最終更新日 2025/12/08

ファングプラス(FANG+)は、話題の株価指数。
その指数に連動した投資信託が、iFreeNEXT FANG+インデックスです。
こちらは、米国ハイテク企業の株価動向を反映する投資信託として注目されています。
FANG+に連動した商品には「おすすめしない」という意見や、掲示板での懸念の声も見られます。
本記事では、公開情報や掲示板の意見をもとに、リスクや留意点を中立的に整理します。
- ・値動きが大きく、短期投資より長期保有向き
- ・信託報酬0.7755%とコストはやや高め
- ・構成がハイテク偏重で下落時の影響も大きい
- ・AI・半導体テーマは追い風だが、過熱・金利上昇に注意
ファングプラスはリスクもありますが、筆者も買っており人気の商品です。
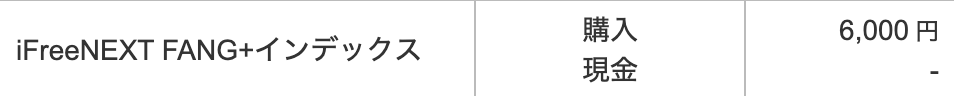
こちらはGMOクリック証券で100円から買えて、人気ランキングでも上位。
\お得キャンペーンを知る/こちらは上場グループであり、無料の口座開設で3,000円もらえるキャンペーンを実施中。

お得な期間限定キャンペーンなので、以下の公式サイトを見ておきましょう。(お早めに)
FANG+(ファングプラス)とは何か?基本解説
FANG+とは、米国の主要ハイテク企業10社(例:Apple、Amazon、Meta、Google、Microsoftなど)で構成される株価指数です。
この指数に連動する国内の投資信託として、iFreeNEXT FANG+インデックスなどがあります。
なお、これらのファンドは「外国株式型インデックスファンド」に分類され、為替リスクなどがあります。
【こちらもチェック!】
>> 【即日現金プレゼントも】無料登録でお金をもらえるキャンペーン、アプリまとめ掲示板で語られる評判、口コミ
掲示板(Yahoo!ファイナンス等)では、FANG+について以下のようなコメントが見られます。
「信託報酬が高く、長期で持つとコストが気になる」
「構成銘柄が偏っていて下落時のダメージが大きい」
「チャートが乱高下していて怖い」
これらは個人投資家の体験・意見であり、必ずしも将来の投資成果を示唆するものではありません。
【こちらもチェック!】
>> 【最新】PayPayポイントを無料で今すぐもらう裏技10選|即日1000円狙える?FANG+(ファングプラス)の評判、口コミ
SNSでは、以下のような投稿もありました。FANG+とゴルナスが仲良く含み益100万円を突破
— シュートザスター (@shootthestar222) September 8, 2025
1月 FANG+700万ゴルナス300万
3月 FANG+20万ゴルナス30万
4月 FANG+50万
2倍以上FANG+に入れとるし、なんなら4月のトランプ関税ショックの底値で買い増しが出来たのもFANG+
今後の推移は分からんけど、今年は4月までに金を買えた人が勝てた相場やったな pic.twitter.com/0bNmNGEEIF
FANG+は下げがオルカンより大きくなるから、両者なかなか拮抗してるw
— ジェイ@投資初心者 (@patience2425) September 22, 2025
まぁ今後FANG+の比率上げるから変わってきちゃうだろうけど pic.twitter.com/6lj2pykKF3
投資信託などの商品が話題であり、言及数も多いようです。
FANG+投資、その常識を疑え!
— 柴ジー (@sibazi_fire50) September 19, 2025
多くの人が知らない5つの真実🤫
1.「最強の10社」は固定ではない常に銘柄が入れ替わる
2.主役はNVIDIAだけじゃない
3.年齢が高いほど「狼狽売り」に注意
4.「全力投資」は危険
5.株価以外の脅威
私は検討中😀#FANGプラス #資産形成 pic.twitter.com/NO5Z7eGuPr
FANG+(ファングプラス)のデメリット・リスクを整理
次に、ファングプラスの主なリスク・デメリットを整理します。
① 信託報酬・運用コスト
iFreeNEXT FANG+インデックスの信託報酬は年率0.7755%程度。
一般的なインデックスファンドよりやや高い水準です。
運用コストはリターンを削る要因となるため、費用面の確認は重要です。
② 変動リスク(ボラティリティ)の大きさ
FANG+では、構成銘柄数が10社と少なく、特定企業の株価に大きく影響されます。
特定銘柄の業績悪化やハイテクセクターの不調により、指数全体が急落する可能性もあります。
FANG+指数の構成銘柄
そもそもFANG+指数を構成する銘柄は以下の10社です。
- Alphabet(アルファベット)
- Amazon(アマゾン)
- Apple(アップル)
- Meta Platforms(メタ・プラットフォームズ)
- Microsoft(マイクロソフト)
- NVIDIA(エヌビディア)
- Broadcom(ブロードコム)
- Netflix(ネットフリックス)
- CrowdStrike(クラウドストライク)
- ServiceNow(サービスナウ)
これらは元の「FANG」の4社(Facebook、Amazon、Netflix、Google)に、現在のテクノロジー業界を牽引する6銘柄が加わったものです。
FANG(元の4社)
- Facebook(現・Meta Platforms)
- Amazon
- Netflix
- Google(現・Alphabet)
追加の6銘柄
- Apple
- Microsoft
- NVIDIA
- Broadcom
- CrowdStrike
- ServiceNow
③ 分散性の低さ・セクター偏重
FANG+は、IT・ハイテク分野に集中しているため、景気後退や金利上昇の影響を受けやすい構造です。
金利が上がると価格が下落しやすい傾向にあります。
④ 業績依存と成長持続性の不確実さ
FANG+を構成する企業が今後も成長を続けられる保証はありません。
AI・半導体などのテーマ性が市場で過熱している場合、調整局面では下落リスクもあります。
⑤ レバレッジ型ファンドはさらに注意が必要
FANG+には、レバレッジ型の商品もあります。
こうしたレバレッジ型FANG+ファンドでは、値動きが大きくなりやすいです。
短期売買向けの商品であり、長期保有には向かない商品と言えます。
ファングプラスなどの投資信託を100円から買える人気証券は?
ファングプラスはリスクもありますが、筆者も買っており人気の商品です。
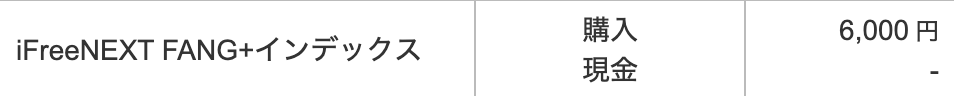
こちらはGMOクリック証券で100円から買えて、人気ランキングでも上位。
\お得キャンペーンを知る/こちらは上場グループであり、無料の口座開設で3,000円もらえるキャンペーンを実施中。

お得な期間限定キャンペーンなので、以下の公式サイトを見ておきましょう。(お早めに)
メリット・選ばれる理由(一般的な見解)
一方で、FANG+には成長企業群にまとめて投資できる点を評価する声もあります。
ここでは、一般的に指摘されるメリットを整理します。
① ハイテク成長企業への間接投資が可能
ファングプラスは、Apple、Amazon、Google、Microsoft など、世界を代表するハイテク企業の株価動向に連動しています。
そのため、個別株を一つひとつ購入しなくても、これらの企業群の成長をまとめて取り込むことができます。
たとえば、AI(人工知能)・クラウドサービス・オンライン広告・半導体といった、近年市場を牽引する分野に分散投資できる点が特徴です。
ただし、構成銘柄の入れ替えやウェイト変更は指数のルールに基づいて行われるため、内容を定期的に確認することが大切です。
② 長期成長テーマへのアクセス手段
ファングプラスは、AI・クラウド・半導体などの分野で世界的な影響力を持つ企業群で構成されています。
こうした企業は、今後のデジタル化や生成AIの進展、インフラ投資の拡大などの恩恵を受ける可能性があります。
ただし、テーマ型投資は流行や市場環境に左右されやすく、テーマの勢いが弱まるとリターンが鈍化する点には注意が必要です。
③ 分散投資の一部としての活用
ファングプラスは、S&P500や全世界株式インデックスとは異なる値動きをすることがあります。
分散ポートフォリオの補完要素として利用される場合があります。
たとえば、国内株式や債券を中心に資産を保有している投資家が、ポートフォリオの一部に「成長分野のリスク資産」として少額組み入れるケースです。
こうすることで、景気拡大局面やハイテク好調時に全体リターンを押し上げる効果を狙えます。
一方で、景気後退局面や金利上昇期には、逆に下落の影響を受けやすいため、資産配分のバランスが重要です。
危ない?危険?今後の見通し・将来性
今後のFANG+のパフォーマンスは、構成銘柄の業績や世界的な金利動向、為替、地政学要因など複数の要因によって左右されます。
AI関連の投資拡大が追い風になる可能性もある一方で、ハイテクセクターの過熱感や金利上昇リスクには注意が必要です。
「上がる」「下がる」といった予測は困難であり、冷静なリスク管理が前提です。
Q&A:ファングプラスでよくある疑問に回答
Q:掲示板では「おすすめしない」との声が多いですが、買わない方がいい?
A:掲示板の意見は個人の主観であり、投資判断の根拠にはできません。
公式の目論見書や運用レポートを確認し、自身のリスク許容度に基づいて判断することが大切です。
Q:今後上がりますか?
A:市場環境によって異なります。
AIや半導体関連の好調が続けば恩恵を受ける可能性はありますが、逆に金利上昇局面では下落リスクもあります。
Global X FANG+ ETF (ASX:FANG) とは何?
「ASX FANG」は、オーストラリア証券取引所(ASX)に上場している「Global X FANG+ ETF (ASX:FANG)」という上場投資信託(ETF)を指します。
このETFは、米国の主要なテクノロジー・インターネット企業10社で構成されるNYSE FANG+指数に連動することを目指しています。
やばい?FANG+(ファングプラス)まとめ
ファングプラス(FANG+)は、高い成長性とリスクを併せ持つハイテク株連動型の投資信託です。
短期的な値動きや一時的なトレンドに流されず、長期・分散・自分のリスク許容度を基準に判断することが重要です。
ファングプラスはリスクもありますが、筆者も買っており人気の商品です。
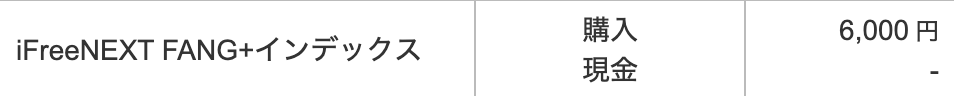
こちらはGMOクリック証券で100円から買えて、人気ランキングでも上位。
\お得キャンペーンを知る/こちらは上場グループであり、無料の口座開設で3,000円もらえるキャンペーンを実施中。

お得な期間限定キャンペーンなので、以下の公式サイトを見ておきましょう。(お早めに)






















